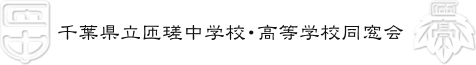松下村塾と匝瑳高校
~今日的同窓会の意味を考える~
大木裕信
 高杉晋作、久坂玄端、吉田稔麿、入江九一、伊藤博文、山縣有朋、前原一誠、品川弥次郎・・・歴史好きでない方でも、幾人かの名前は聞いたことがあるだろう。いずれも、幕末から明治という激動の日本史の中にその名前を刻み込んだ長州人たちである。そして、彼らを一つの言葉でくくるとすれば、それは「同窓生」と言うことになる。
高杉晋作、久坂玄端、吉田稔麿、入江九一、伊藤博文、山縣有朋、前原一誠、品川弥次郎・・・歴史好きでない方でも、幾人かの名前は聞いたことがあるだろう。いずれも、幕末から明治という激動の日本史の中にその名前を刻み込んだ長州人たちである。そして、彼らを一つの言葉でくくるとすれば、それは「同窓生」と言うことになる。
当時の長州藩において、その後の倒幕につながる思想形成に大きな影響を与えた人物が、かの吉田松陰。彼が主宰した学舎が「松下村塾」。冒頭の偉人たちは、皆、その塾生であり同窓の士でもある。激動の時代である故、幕末を見ることなく20代で生涯を閉じた者もあれば、明治という近代日本の礎づくりに元老として寄与し続けた者もいる。あの世と言うものがあるとすれば、彼らは再び吉田松陰の下に集まり、自らが命を懸けた国のあり方を、そして現在の日本の行く末を、若き塾生に戻って議論しているのではないだろうか。志を共にした同窓の士とはそういうものであろう。同窓会の会長を拝命してから、そんなことをぼんやりと考えている。
当たり前であるが、松下村塾と匝瑳高校は違う。彼らが為さんとしたことと、私たちの社会への関わりは比べる意味もない。現代に生きる私たちは、それぞれの場所において、日々の生活をきちんと営み、目の前の仕事をこなしていく。それが、大事であろうが小事であろうが、派手であろうが地味であろうが、当たり前に続いていく日々の暮しをきちんとコントロールして生き続ける。市井の生活者として連綿と続くその努力が、地域を支え、社会に貢献することになる・・・匝瑳高校の卒業生は、現代社会におけるそういう存在なのだと思うのである。
かつて、匝瑳高校で学んだ私たちは、今や、万を超える同窓の士となり、多くの分野において社会に関わり、この国の営みに携わり続けている。そして、改めて考える。多種多様な社会生活の場で現出し続けている全ての卒業生の途方もないエネルギー、それを繋ぎ止め、維持して発展させること、それをなし得る唯一の媒体こそ同窓会であるはずだと・・・。
「同窓の士」の思いやエネルギーを受け止め、母校との関係を築き、同窓生同士の絆もつなげていく、卒業しても母校や同窓生とずっと繋がっていられる、そういう感覚を持てるような同窓会を構築していきたいと思っています。
今、この時代に、なぜ、何のために同窓会があるのか、その意味をしっかり考え活動していくつもりです。会員の皆様のご指導、ご協力を心よりお願い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。