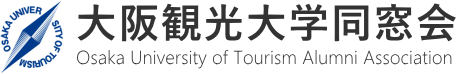浮田 健司 さん (1期生)
京都ブライトンホテル 宿泊サービス課 勤務
Q: まずは簡単な自己紹介をお願いします。卒業年度と学部学科、そしてゼミの先生のお名前を教えてください。
A: 浮田健司です。平成15年度に観光学部観光学科観光文化コースを卒業しました。ゼミの先生は浦達雄先生です。
Q: 現在のお勤め先と役職を教えていただけますか?
A: 現在は、株式会社ブライトンコーポレーションの京都ブライトンホテルで、宿泊部宿泊サービス課フロントサービスの支配人をしています。2023年4月から2024年7月までは、副総支配人のアシスタントとして、宿泊部の業務をサポートしていました。
Q: ホテル業界を選んだ理由は何ですか?また、これまでの転職経験はありますか?
A: 大学在学中に、「ホスピタリティ」と「対価を得る」という2つの概念が結びつく仕事に興味を持ちました。ホスピタリティの面でホテルが格が高いと思い、ホテル業界への就職を決め、京都ブライトンホテルに入社しました。転職はしていません。
Q: ホテル業界を選んだことは成功だったと感じますか?
A: 体力的に厳しいことも多かったですが、ホテルでの仕事は私にとって楽しいものですし、今も続けています。ですから、ホテル業界を選んで良かったと感じています。
Q: 現在は具体的にどのようなお仕事をされていますか?
A: フロントサービスとして、フロント(レセプション)、コンシェルジュ、予約センターの3つのチームの責任者をしています。プレイングマネージャーとして、勤務時間の約70%はフロント業務に従事し、残りの30%でマネジメントと、コンシェルジュ・予約チームのサポートをしています。
Q: 現在のお仕事のやりがいや、支配人になる前のお話を聞かせてください。
A: ホテル業界に入るまでは事業形態について詳しく知りませんでしたが、現場に入ると、様々な特性を持つビジネスだと分かりました。私たちはサービスと客室を提供しますが、これは「在庫を持てないビジネス」です。その日の在庫を確実に使い切るための考え方が不可欠です。 また、ホテル内の物は開業した日をピークに劣化していくので、お客様に古さを感じさせない工夫が必要です。これは大規模なリノベーションで回復を図ることもあれば、スタッフの「真心や気配り」でカバーすることもあります。2004年から2005年頃にはIT事情が大きく変化し、ITと既存のおもてなしを組み合わせてお客様に満足していただく方法を考えることが面白かったです。
Q: 印象に残っている成功体験や、お客様から嬉しい言葉をもらったエピソードはありますか?
A: 私はお客様の顔や名前をあまり覚えられないタイプなので、むしろお客様が満足するサービスのスキームを考え、それを接客が得意なスタッフに任せることを主に取り組んできました。 ホテルでのIT技術の進化を組み合わせていたとき、Appleが発表したiPhoneは、インターネットの登場に匹敵するほどの衝撃でした。その当時、大阪のホテルの開業準備室にいた私は、「選ばれるホテル」になるため、ITインフラの刷新を経営陣に提案しました。他のホテルがまだ導入していない無料Wi-Fiを、無料かつ大規模なキャパシティで提供するよう主張したことは、これまでのキャリアで最も情熱を燃やし、達成感があった仕事として記憶に残っています。
Q: 大阪観光大学での学びが、現在の仕事でどのように活かされていますか?
A: 浦先生のゼミでは「地域観光」について学びました。特定の場所へ足を運び、フィールドワークで歩き、実際に体感したことに評価をつけるという研究をしていたんです。この「実際に足を使って調べる」という姿勢は、今も私の仕事に活きています。 例えば、ホテルの客室は200部屋ほどありますが、それらを単に「客室」として捉えてはいけません。1部屋1部屋状況が異なり、壁の裏の配管も、日当たりも、コンディションも全て違います。そのため、私は部屋番号だけで仕事をするのではなく、お客様がその部屋で何を感じるのかを理解するために、自ら足を運ぶようにしています。お客様のネガティブな意見に対して、電話一本で「これはこういうものです」と答えるのは簡単ですが、自分で状況を体感して対応することが重要だと考えています。
Q: 大学で学んで良かったこと、プライベートで活かされていることはありますか?
A: 大学で学んで良かったことの一つは、「旅行が好きな人が必ずしも旅行サービスの提供者になれるわけではない」という事実に出会えたことです。私はホスピタリティで賃金を稼ぐという提供者の視点で物事を考えますが、学生時代には旅行を消費者の行動として楽しむ人が多く、その価値観の差を感じました。観光学という学びの中で、多様な視点があることを知り、社会に出てからも、お客様や同僚の異なる価値観を理解する上で役立っています。例えば、同僚が「ホテルを楽しく輝かせたい」という視点で考える一方で、私は「それが収益につながるのか、単なる自己犠牲ではないのか」というビジネスの視点も持ちます。奉仕活動ではなく、プロとして対価を得るためにサービスを提供することを、大学時代の多様な人との交流を通じて学びました。 プライベートでは、浦先生のゼミで「足を使って様々なことを知り、見て、体験する」という学びから、私の趣味が「ウォーキング」に落ち着きました。ここ10年ほど「街歩き」を続けていて、これは仕事にも大変活きています。
Q: 学生時代に印象に残っている授業や先生とのエピソードを教えてください。
A: 浦先生の授業で、「出没!アド街ック天国」というテレビ番組を見せてもらったことが印象に残っています。先生はご自身の研究が、ある町に行って見て調べて体験し、人から話を聞いて、その町の観光ポテンシャルに点数をつけることだと説明されました。授業で直接フィールドワークや観光資源の評価について説明されても分かりにくかったのですが、テレビ番組を見ることで、「この町に行って20個のものをランキング付けし、タレントがそれを紹介することで、他の人が行ってみたくなる。これこそが観光研究だ」ということが明確に理解できました。 浦先生は「変わっている」方でした。1年生や2年生の時は「変な人だな」と思っていましたが、変わったことをする人が面白いと感じ、先生のゼミを選びました。面白いエピソードとして、「これ僕どこで髪切ったと思いますか」という話があって、当然僕には分かるわけもなく。すると「ちょっと中国に行ってきて、中国で切ってきたんです。日本だったら髪切って黒染めして3000円くらい取られるんですけど、中国だったら500円ですよ、アハハ」とか言っていたんです。すごいなと思いましたが、それは「実際に行ってみてやってみる」をまさに体現されているなと思って。「街に行けば散髪屋なんてたくさんあるわけで、僕ら欧米人のヘアサロンに行くよりも、東アジアのヘアサロンに行けば別に髪質もそんなに大きく変わるわけではないし。黒染めなんか安いですよ!」などとあっけらかんとおっしゃっていました。
Q: 今、大阪観光大学に通う在学生に向けてメッセージをお願いします。
A: 研究や学びは一朝一夕でできるものではありません。大切なのは「好きなことをまず続けていくこと」、そして「なぜ観光学をやってみようと思ったのか、その気持ちを絶対に忘れないこと」です。その気持ちを持ち続け、勉強を続けることで、いずれ何かの要素が繋がり、自分の人生を豊かにしてくれるはずです。特に観光学は平和に深く関連する学問だと思います。その気持ちを忘れずに勉強を続けてください。そうすれば、観光学を通じて社会や家族にどう貢献していくのか、自分の役割が見えてくるでしょう。
Q: 大阪観光大学の卒業生、OB・OGの仲間へメッセージをお願いします。
A: 私たちのような小規模な単科大学の卒業生にとって、自分の人生を豊かにするには、大学を「問題解決のプラットフォーム」として活用することが非常に重要だと感じています。 先程、図書館で古い論文集を見つけ、その中に「観光におけるICカードの活用」や「労働時間と自由時間」というタイトルの論文がありました。まさに現在の観光事業でICカードの利用は当たり前になっており、観光客は現地で電子マネーを購入し、コンビニや電車で利用しています。私たちが学生だった頃はICカードがまだ普及していませんでしたが、「労働時間と自由時間」という考え方と合わせて、当時から未来を予見し、観光に対してこうあるべきだと提言していた研究者が本学にいたということに心強さを感じました。 現在、大学の論文集は「研究論集」と名称が変わり、大学のウェブサイトからPDFで読むことができます。今、仕事で抱えている課題の解決策が、もしかしたらそこにあるかもしれません。一つのキーワードやタイトルが、今の課題を解決するヒントになる可能性を秘めています。私たちの大学というプラットフォームにアクセスすることは誰でもできます。そこにアクセスすれば、この業界の問題解決のヒントがあるはずです。先生方も助けるヒントをきちんと持っています。ぜひ活用して、世の中がどのように変わっていくのかを体験してみてください。
Q: 大阪観光大学の教職員の方々へメッセージをお願いします。
A: 私個人としては、2000年の就職氷河期をモラトリアムとして人生を謳歌しました。もし人生をやり直せるなら、やはり大学時代に戻りたいと答えるでしょう。 コンプライアンスが厳しく、昔のような無茶は許されない時代ですが、学生たちが将来「大学時代に戻りたかったね」と思ってもらえるような、思い出深い学生生活を提供できるよう、学生と接していただければと思います。
Q: 最後に、何か伝えたいことはありますか?
A: はい、卒業生のみなさんには同窓会のイベントと幹事会にはぜひ参加してほしいと思っています。
インタビュー後記:
今回のインタビューでは、大学での学びが実社会でいかに活かされているかを、具体的なエピソードを交えてお話しいただきました。特に、ホスピタリティをビジネスとして捉える考え方や、「問題解決のプラットフォーム」として大学を活用するという視点は、社会で活躍するOB・OGや観光学を学ぶ学生にとって、大きな示唆を与えてくれるものだと思います。
また、観光学が「平和」に深く関連するというお言葉や、就職氷河期を乗り越えてきた経験から語られる力強いメッセージには、多くの読者が勇気を与えられるでしょう。