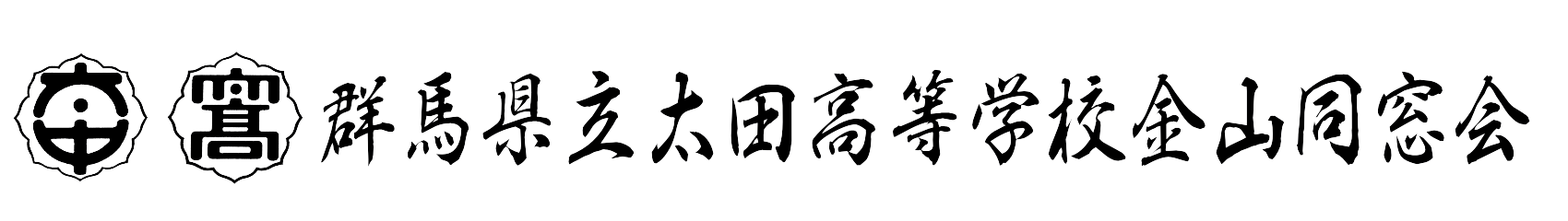田中哲二先生講演会
令和7年9月27日(土)
熊谷市妻沼中央公民館
妻沼支部の創立1周年を記念して、国際的に活躍中の郷土の名士田中哲二先生(金山京浜同窓会長でもある)の講演会が催されました。
講演に先立ち、生徒会長を含む現役の太田高校生と田中先生の懇談の機会を頂きました。生徒たちからは「第二外国語として有用な言語は?」「海外から見て日本の弱点はどこにあるか?」「真の国際人になるために必要なことは何か?」等々の質問が出されましたが、その一つ一つに丁寧に応答していただきました。
途中から、太田高校卒業生でもある清水前太田市長及び長谷川衆議院議員も合流されて、質疑・応答の幅が広がり有意義な時間となりました。生徒たちは緊張の中にありながらも大きな刺激を受けたように見受けられました。
講演会には150名ほどの参加者があり、公民館2階の会場は超満員の盛況となりました。冒頭、小林妻沼支部長より田中哲二先生の講演会実現に至るまでの経緯の説明がありました。 小林妻沼支部長より、今回は、太田高校卒業生だけにとどまらず、田中先生の広い知見を先生出身の地元とも共有したいということで、参加者の枠をより大きく広げたとの説明がありました。こうした小林支部長の熱意が多くの人を動かし、支部主催のイヴェントとしては異例の大掛かりなものになりました。
田中先生の講演会は、毎年の金山同窓会の新年総会あいさつでの時間不足の補完でもあるというユーモアたっぷりの話に始まり、ユーラシアを中心とする国際情勢・安全保障問題、大きな影響を受けた郷土の歴史と精神風土、先生ご自身の生き様、日本人が国際人になるための必要条件等様々な問題にも触れ、予定時間の90分はアッという間に過ぎてしまいました。
とくに第二次大戦後の国際政治を牛耳ってきた米国・ロシア・中国の三角の関係性を先生独自の鋭い視点で構成されたキッシンジャー博士の二等辺三角形論など、この講演会ならではの内容のものがたくさん含まれていました。また、現地経験を背景にロシアサイドから見た露・ウクライナ戦争の必然性など、西側情報に依存する日本のマスコミでは報道されない話題も多く、全く啓蒙の名に値する講演会となりました。
講演レジュメに掲げられた「伝えておきたい七つのポイント」を取り纏めると次のようになります。
- 高まる中央アジア・南コーカサス<7か国>の地政学的重要性。
- 露・ウクライナ戦争の性格と米・中・露の関係(キッシンジャー博士の二等辺三角形論の蹉跌)。
- 実は歴史・地勢的にデリケートな関係にある中・露関係、西側の認識は「中・露蜜月」(クリミヤ半島併合/露・ウクライナ戦争に存在する中国ファクター)。
- 当面の中国・米国への対応(地政学的に米・中の狭間に位置する日本の宿命と中・長期的関係の展望と覚悟)。
- 郷土の歴史と文化、自然環境の厳しさの影響を受けた精神風土のアイデンティティー(「上武・東毛文化」ないし「利根川中流域文化」)。
- 日本人の国際化進展に必要な条件(海外駐在型と短期訪問型では差異)。
- 結果的な「私の生き方」(minorityに寄り添って、時にminorityを代表する覚悟)。
惜しむらくは、時間の関係で、レジュメ後半のすべてが語れられなかったことと質疑応答の時間が限られてしまいましたので、また別の機会に5~7についてはより具体的に伺う機会があってもいいのではないかという感じがしました。
また、講演会終了後に田中先生の同郷小・中学校のご友人(男子13人、女子13人の小クラスが9年間継続)と再会の場が設けられて、会場は懐かしく温かい雰囲気に包まれました。
講演会終了後は、午後5時より妻沼「和とう」において懇親会が催されました。金山同窓会の他の支部長を含め参会者全員挨拶と旧交を温める多くの出会いもあって、講演会に続き充実した意義あるオープンな妻沼支部活動となりました。